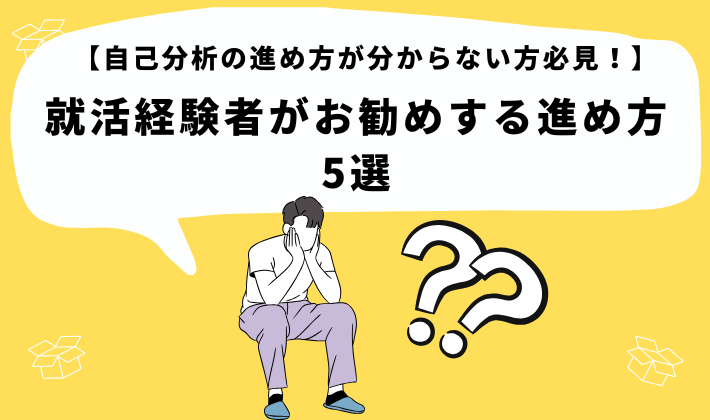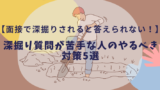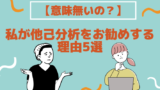こんにちは、はたてです!
就活では選考対策や企業分析など色々とやらないといけない事がありますが、その中の1つに自己分析がありますよね。
皆さん自己分析は順調ですか?
私も自己分析を始めた当初は進め方がそもそも分からなかったりと、色々苦労した経験があります。
なので今回は私が実際に自己分析を行って、この方法は良かったと思える進め方を5つ紹介します。
- 自己分析の進め方が分からない方
- 自己分析の進め方に関する経験者のお勧めを知りたい方
自己分析の目的
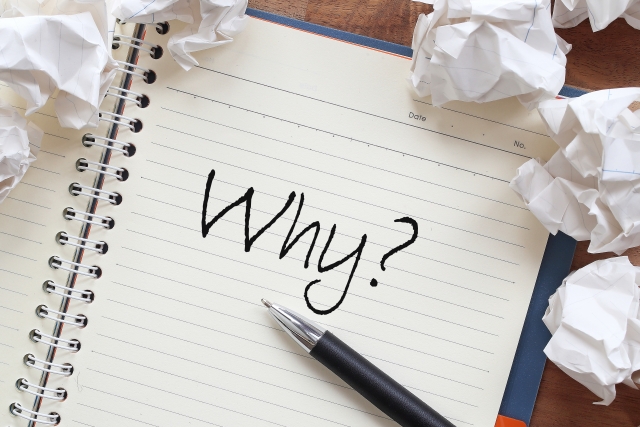
本題に入る前に自己分析を実施するそもそもの目的について改めて整理しておきましょう。
人によって色々と意見はあると思いますが、私が思う自己分析の目的は3点あります。
- 面接での深掘り質問対策を実施する為
- 自分の主張に説得力を持たせる為
- 自分自身に関しての理解を深めて言語化する為
以下で詳細を説明しますね。
1. 面接での深掘り質問対策を実施する為
面接では面接官からの質問に対して就活生が自分の意見や考えを回答するのですが、その就活生の回答に対して更に面接官が詳しい内容を質問してくる場合があります。
これが皆さんご存知の深掘り質問です。
苦手意識を持つ方も多いと思いますが、この質問対策が出来ていないと内定獲得が遠ざかってしまうので、ちゃんと時間をかけて対策する必要があります。
では深掘り質問の対策を実施するにはどうすれば良いのでしょうか。
それは端的に言えば「面接官から深掘りされる前に自分自身に関して予め具体的に理解出来ている状態にする」という事になります。
ではそのような状態にするにはどうすれば良いのかという事なのですが、そこで自己分析が登場します。
自己分析をしっかりやり込む事で面接本番で面接官から深掘り質問を聞かれる前に、自分自身で自分自身について深掘る事が出来るのです。
自己分析では自分自身に対する理解を深める為に、自分が過去に経験した内容について具体的に思い出す作業が必要となります。
「小学生の時に〇〇な事があったな」とか「高校生の時は△△な出来事に直面したな」とかのような思い出ですね。
加えてそれらの出来事に対してより具体的に当時の自分の感情や考えをまとめていきます。
「楽しい・辛い」といった感情や、「取り組んだ理由・継続出来た要因・困難に対してどう思ったか」といった考えを具体的に深掘るのです。
このような深掘りの作業をやり込んでいくと自分自身をより深く理解する事が出来ます。
そして同時に予め自己分析を通じて自分自身に対して深掘りしているので、面接本番で面接官から深掘り質問を聞かれても対応出来るようになるのです。
深掘り質問の具体的な対策方法は以下の記事で記載していますので、もしまだ対策に不安を感じている方がいれば是非ご覧ください。
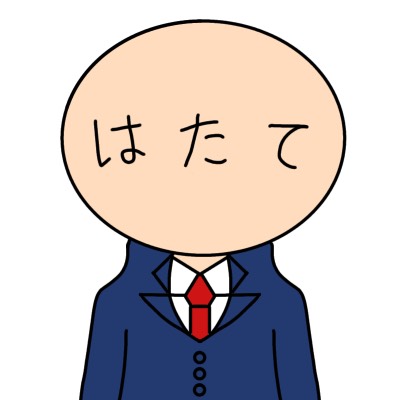
自己分析を通じて深掘り質問対策の全てを抑える事が出来る訳ではありません。
しかし自己分析を実施すれば、より自信を持って面接官からの深掘り質問に挑めると思いますよ。
2. 自分の主張に説得力を持たせる為
就活では様々な場面で自分の意見を主張する機会があります。
イメージしやすい内容ですと、例えばESでの志望動機や面接での就活軸等ですね。
このような場面で自分の意見を主張する際、単純に自分の考えている事や、やりたい事等をそのまま伝えても企業側は納得してくれません。
例えば面接で強みに関して聞かれた時に「私はコミュニケーション力が強みです」と伝えても、それだけでは面接官は納得してくれないでしょう。
なぜならその意見に関係する根拠が無いからです。
では根拠を説明するにはどうすれば良いのでしょうか。
ここで私がよく活用していたのは、自分が過去に経験した実体験の話と主張を関連づける事です。
「過去に○○のような経験や出来事があったので、私の強みはコミュニケーション力です」というような構成で自分の意見に根拠を加えながら主張していました。
こうする事で事実の出来事をベースに根拠を伝える事が出来るので、企業側もより就活生側の主張を理解してくれるでしょう。
また実体験を根拠とするのはもう1つ良い事があります。
それはその根拠に対して面接官から深掘りされても対応しやすいという事です。
先程の深掘り質問対策で説明したように、面接では就活生の回答に対して面接官から更に詳しい内容を聞かれる深掘り質問があります。
そしてこの深掘り質問は自分の主張に関係する根拠に対しても聞かれる場合があるのです。
深掘り質問に苦手意識を持つ就活生は一定数いると思いますが、そこまで怖がる必要はありません。
なぜなら実体験であれば多少具体的な内容を聞かれたとしても回答に詰まる可能性が低いからです。
実際に自分が経験した事なので、小学生時代など相当昔の話でない限り、ある程度の内容は覚えていますよね。
なので根拠を実体験ベースにすると面接官から深掘り質問を聞かれても対応しやすくなるという訳です。
3. 自分自身に関しての理解を深めて言語化する為
自己分析を通じて自分自身に関する理解を深める事は、自己分析を実施する上での基本的な目的の1つです。
多くの就活サイトや書籍で紹介されていますので、皆さんも「それは分かってるよ」と思った事でしょう。
この基本的な要素に加えて私が皆さんに注目してほしいのは、「言語化」というキーワードです。
自己分析は先程説明したように自分自身に関して理解を深める目的があるのですが、皆さんご想像の通りある程度自分の特徴については何となく想像がつきますよね。
日頃の生活から「私は誰とでも臆せず話す事が出来るな」とか、「新しい事にも果敢に挑戦する意欲が強いな」とか、ある程度自分の特徴についてふんわりと思い浮かべる事が出来るでしょう。
しかし就活ではこの「何となく」や「ふんわり」といった曖昧な状態は危険です。
なぜなら就活では自分の頭の中にある感情や考えを言語化しなければならない機会が非常に多いからです。
自分のイメージだけに留めず、そのイメージを相手に言葉や文字で伝えられないと内定獲得には近づけません。
その機会の多くは選考の場で訪れます。
ESや面接で強みや弱み、就活軸、志望企業で将来やりたい事など、自分の考えを言葉や文字で伝えなければいけません。
「頭の中で大枠がイメージ出来ているから簡単だよ」と思う方がいるかもしれませんが、実際にやってみれば分かります。
自分のイメージを言語化する事は結構難しいです。
例えば選考の最初の段階で取り組むESで問いに対する文章を書こうとすると、中々文章が書けないなんて事が起こってしまうんですよね。
しかしここで自己分析を実施しておくと予め自分の頭の中を文字に起こして言語化しているので、全くの0から言語化するよりも作業が楽になります。
ESは人によっては多くの企業に対して作成しなければならないので、少しでも言語化しやすい状態に出来ていると、より早く効率的にESを作成出来るようになりますよ。
やって良かった自己分析の進め方

それでは私がやって良かったと思う自己分析の進め方について5つ紹介します。
自己分析に苦戦している方は1つでも良いので真似してみてください。
1. 楽しかった事、成果を出せた事から考え始める
自己分析は楽しかった事や成果を出せた事に関する内容から作業を進めていきましょう。
自分にとってプラスな感情の内容から作業を進めると、少しでもやる気を維持しながら取り組めると思います。
一方で自分の弱みや失敗した事等、マイナスな感情の内容から作業を進めると段々気分が落ち込んでくるので集中力が続きません。
自己分析は就活で重要となる作業の中でも、相当な体力が必要となる作業です。
実際に自己分析を行った人は実感したかもしれませんが、たった30分の自己分析を行なっただけでも結構疲れますよね。
なので少しでも、やる気や集中力を維持出来るような進め方で作業する事をお勧めします。
2. 思い出せるだけ記憶を遡る
自己分析を行う際には、楽しかった事や心を動かされた経験など何かテーマを決めながら過去の自分の記憶を振り返ると思います。
その際には出来る限り過去に遡ってみましょう。
私は幼稚園生時代の記憶も少しだけ残っていたので、その頃から振り返って自己分析をしていました。
出来るだけ過去を遡る事で自分がどのような性格なのか、どのような特徴を持つ人間なのかよく理解出来ます。
幼稚園生や小学生の時から今でも変わらない事があれば、それはもう今後変わる事がないであろう自分の性格だと分かるでしょう。
例えば「小さい頃から何かに興味を持つと周りが見えなくなるような性格だった事が現在も続いている」ようであれば、自分は「視野が狭くなってしまうかもしれないけど、興味のある事に対しては高い集中力を持って取り組む事が出来る人間」だと理解出来ますよね。
また、小さい頃からの思考が変わる場合でも自分を理解するきっかけにする事が出来ます。
その時にはいつ変わったのか、なぜ変わったのかに注目して自己分析してみてください。
自分の思考が変わったその瞬間を捉える事で、どのように今の自分が形成されたのか理解する事が出来ますよ。
一方で高校生や大学生時代のような浅い過去だけで自己分析してしまうと、上記の分析が出来ません。
昔の話を思い出す事は難しいですが、なるべく過去の記憶を遡って自分について分析してみましょう。
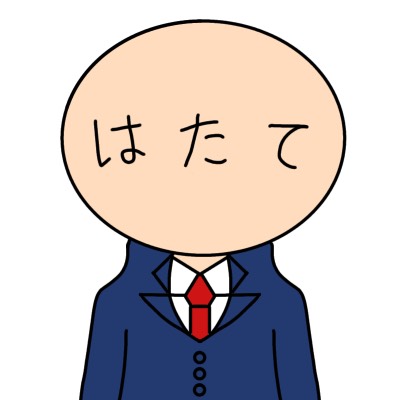
自分の頭の中だけで思い出す事が難しければ、親に昔の話を聞いたり、アルバムを見せてもらったりすれば記憶を思い出すきっかけになるかもしれないですね。
3. 分析方法の型を作る
いざ、「自己分析を始めよう!」と思ってもどのような事から考え始めれば良いのか分からない方は多いと思います。
なのでそのような方はいきなり自己分析を始めるのではなく、自己分析を実施する為にはそもそも何を考えなければいけないのか整理しましょう。
例えばガクチカに関して自己分析を始めようとした時、皆さんはどのような事について考えれば自己分析が出来た事になると思いますか。
正解はありませんので、ご自身なりに考えてみてください。
私は以下の要素を考える必要があると思います。
- なぜその活動に取り組もうと思ったのか(動機)
- なぜその活動を頑張れたのか(モチベーションの源泉)
- どのような課題や問題に直面したのか(課題)
- なぜその課題や問題が発生したのか(原因)
- 課題や問題に対してどのように対応したのか(施策)
- 対応した結果どうなったのか(結果)
- その結果から自分は何を学んだのか(学び)
上記のような考え方の型を作って、過去に経験した様々な活動に対して自己分析をしていました。
自己分析は考え始めるスタートダッシュが上手く決まらないと、何について考えれば良いのかイメージ出来なくなってしまい、全く手が進まない状況になってしまいます。
なのでこのように1度型を作ってその型を基準に自己分析を行うと、先ず何から考えれば良いのか手順が明確になるので、格段に自己分析がやりやすくなると思いますよ。
4. 「なぜ?」と自分に問い続けて深く分析する
自己分析を実施するにあたって「なぜ?」と自分自身に問いかけ続ける事は非常に大切な意識です。
「なぜ?」と自分に問いかける事で、より深い自己分析が出来るようになります。
自己分析はより深く行う事で、自分の深層にある考え方や本心に気づく事が出来ますからね。
やり方についても説明します。
例えば、塾講師のアルバイトを始めた動機を考えて以下のような自分の想いに気づく事が出来たとします。
私は受験を意識し始めた高校生の時、今通えている大学に合格するには圧倒的に学力が足りなかった。そして大学合格の為に必死で勉強したけど成績が思い通りに上がらず、かなり苦労した経験がある。それでも頑張って勉強を続けて何とか志望校に合格出来たので、受験生時代に頑張って本当に良かった。そのような経験を生かして、今の受験生を支援したいと考えるようになり塾講師のアルバイトを選んだ。また、社会人になったら自分の考えや意見を相手に分かりやすく伝えるスキルが必要になると思い、塾講師であればそのスキルが鍛えられると思った事も理由である。
自己分析を通して上記のようなアルバイト先を選択した動機が分かりましたね。
次はこの動機に対して「なぜ?」と問いかけてみましょう。
こんな感じで問いかけを行います。
- なぜそもそも受験開始時に圧倒的に学力が足りなかったのか
- なぜ志望校合格に向けて頑張る事が出来たのか
- なぜ自分の経験を他の人に役立たせたいと思ったのか
- なぜ自分の考えや意見を相手に分かりやすく伝えるスキルが社会人に必要だと思ったのか
上記の問いかけに対して再度回答を考えてみましょう。
そしてまた、考えた回答に対して「なぜ?」と問いかけるのです。
このように「なぜ?」を繰り返す事によって、どんどん深い自己分析が出来るようになりますよ。
深い自己分析が出来ると後の面接対策が楽になる
自己分析の目的の1つ目に紹介した「面接での深掘り質問対策を実施する為」で記載したように自己分析を通じて深掘り質問対策が出来る事を紹介しましたが、その際に深い自己分析を行う事でより面接対策を楽にする事が出来ます。
なぜなら面接官から飛んでくる深掘り質問のパターンは様々あるのですが、「なぜ?」と具体的な内容を質問してくるケースが割と多いからです。
なので自己分析を通して「なぜ?」と自分に対して問い続けていれば、実際の本番で面接官から質問されたとしても、自信をもって回答出来る状態になります。
面接官から「なぜ?」と聞かれた内容が予め自己分析で考えていた内容であれば、その考えていた内容をそのまま回答すれば良いだけですからね。
自分に問い続ける事は予想以上に精神的に疲れる作業ではありますが、この作業を行えば必ずどこかのタイミングで自分の就活に活かす事が出来るので、踏ん張ってやり切りましょう。
5. 他人から見た自分についても把握する
自己分析は自分自身をより深く理解する為の作業である事から、1人で実施するべきだと思う方がいるかもしれません。
ですが、私は他の人と協力して進める事もお勧めします。
なぜなら自分だけでは気づけない視点で自分を理解する事が出来るからです。
自分では「私はこんな特徴を持つ人間だ!」と思っていても、他の人は全然違う特徴に注目している場合があります。
もしかしたら自分が思っている事とは逆の事を他の人は思っているかもしれません。
自分が想像していた事とは異なる視点で自分自身をより深く理解する事が出来ますので、是非、大学の友人や先輩、両親など自分以外の人と一緒に自己分析をやってみましょう。
他の人に自己分析を手伝ってもらう場合は、他己分析をお願いすると良いでしょう。
相手から見た自分について色々と知る事が出来ますよ。
他己分析についてはこちらの記事で詳細を記載しているので是非ご覧ください。
自己分析を進める上での注意点

自己分析は何をすれば良いかという明確な正解がありません。
なので進め方も人によって様々あります。
とはいえ、闇雲に進めれば良いというわけでもないのが難しい所ですよね。
そんな自己分析ですが、一方で注意するべき事に関してはある程度多くの就活生に共通していると思います。
私の経験を踏まえると2点注意するべき事があるので、これから作業を開始する方や、作業中の方は気をつけてください。
1. 考えすぎて時間を使いすぎない
過去の記憶を思い出す際には次々と記憶を思い出せる時があれば、全く思い出せない時もあると思います。
ポンポン過去の記憶が出てくるのなら、そのリズムのまま思い出していけば良いですね。
しかし全く思い出せない場合や、ある程度思い出してこれ以上記憶が出てこない場合は、考える事にあまり時間を使いすぎないようにしましょう。
思い出せない時は本当に思い出せないですからね。
逆に自己分析とは全然関係無い事をしている時に、フッと思い出せる事もあります。
少し考える程度であれば良いですが、10分20分も考えるのは時間が勿体無いです。
思い出せない時は1度キッパリ諦めて、時間を空けてからまた思い出してみましょう。
2. 強みや弱みなどの特徴を1つに絞ろうとしない
自己分析を通じて自分の強みや弱み、どんな時にモチベーションが上がるのか等のような自分の特徴について理解を深めていきます。
この時に自分の特徴を1つに絞る事に拘る必要はありません。
例えば自己分析を進めていくうちに自分の強みとして取り挙げられる要素が以下のように幾つか出てきたとしましょう。
- 誰とでも臆せず話す事が出来る
- 1つの事を諦めずにやり続ける事が出来る
- 今まで経験した事が無くても果敢に挑戦する事が出来る
- 周りの人を巻き込んでチームとして成果を出す事が出来る
これらの要素が出てきた時に「この中で私にとって1番強みとして言えるのは1番目の内容だから、就活ではこの1番目の要素だけを強みとしてアピールしよう」と考える方がいるかもしれません。
ですが、私としてはどの要素も自分の強みである事に変わりはないので、1つに絞るのは勿体無いと思います。
せっかく自分の強みが複数あると分かったのであれば、それら全ての要素を有効活用していきましょう。
私がお勧めするのは複数出た自分の特徴を1つに絞るのではなく、企業によって使い分ける方法です。
先程例に挙げた強みで言えば、4つのうち1つに絞るのではなく、企業によってどの強みを伝えれば1番自分のアピールに繋がるか考えて使い分けましょう。
そのような考え方が出来れば、自分をアピールする為の手札を沢山持つ事が出来るようになりますよ。
自己分析のやる気が出ない時の対処法

あくまで私の意見ですが、自己分析の作業は基本的に楽しくないです。
勿論自分でも知らなかった一面を知る事が出来る楽しさも少しはあるのですが、それ以上に自分自身に対して深掘りしていく作業で頭が疲れます。
というか自己分析に限らず就活自体が面倒臭いので、自己分析も楽しくありません。
友人と遊んだり趣味に時間を使えるなら、そっちを優先したいのが私の本音です。
恐らく皆さんも同じように思っている部分があるのではないでしょうか。
なので腰を据えて「さぁやるぞ!」というような意気込みで自己分析を行うやる気は中々出てこないと思います。
そんな時に私がお勧めするのは、隙間時間を活用する事です。
私が活用していた隙間時間は主に以下の3つです。
- 移動中
- バイトの休憩時間
- 予定と予定の間にある時間
どんなにやりたくない自己分析でも隙間時間であれば最後まで集中力を継続する事が出来ました。
また、上記のような隙間時間は携帯をボーっと見てしまったりして何もしない無駄な時間になってしまう事が多いですよね。
当時の私はそのような時間を自己分析の時間に充てられたので、効率的に就活を進められたと思います。
加えて私は隙間時間に自己分析を行うメリットがもう1つあると思っています。
それは、隙間時間に行う事で昔の記憶を思い出せる場合がある事です。
前の部分で説明した通り、自己分析では自分の過去の出来事を思い出す作業が必要になります。
ですが、まとまった時間を設けて自己分析の作業をしていても思い出せない内容が出てくる事もあるでしょう。
私の経験上、その時に思い出せない記憶は、その時にどれだけ時間をかけても思い出せる事は少ないです。
一方で時間を変えて隙間時間に少しだけでも自己分析に取り組む事で、ハッと思い出せる事があります。
まさに天から突然降りてくるような感覚です。
自己分析の為にまとまった時間を取る事も大切ではありますが、このように隙間時間を活用しながら作業を進めていくと集中力や記憶の観点で大きなメリットがありますよ。
私がお勧めする活用すべき隙間時間は移動時間です。
皆さんは移動時間中に何をしている事が多いですか?
音楽を聴いている人がいれば、風景を眺めている人、何か考え事をしている人など色々な人がいると思います。
私は是非この時間を就活の時間に充ててほしいと思います。
例えば大学までの通学時間やバイト先までの通勤時間、友人と約束した集合場所へ向かう時間など、1日を過ごす中で移動時間は沢山ありますよね。
1回あたりの移動時間は様々あると思いますが、30分以上消費しているケースが多いのではないでしょうか。
この移動時間を全て就活に使えたら今まで以上に就活が進められると思いませんか?
私はこの考えから一時期、移動時間の多くを就活の為に使っていました(サボった時もあるので“全て“ではなく“多く“と表現しています)。
特に移動時間で考えていたのは自己分析と面接での想定質問でした。
自己分析では、分析を行う時には何かテーマを決めて自分の過去の記憶を思い出しますよね。
例えば「何かやり遂げた事」というテーマで自己分析を行っていたとします。
テーマを決めたら、歩いている時や電車に乗っている時に「何か自分の人生の中でやり遂げた事はないかな〜」と記憶を掘り起こしていました。
そしてもし何か思い出す事が出来たら、都度スマホのメモ帳アプリにメモしていました。
このように隙間時間を活用して、少しでも効率的に就活が進められるように行動していましたね。
自己分析に対してマイナスの感情を抱く事は間違いではない
自己分析に関してネットで色々と調べていた時に1つ驚いた事があります。
それは様々なサイトが自己分析に対する気持ち悪いという感情について記事を作成していた事です。
私自身も自己分析は楽しくないと思っているのですが、どうやら気持ち悪いというより強いマイナスの感情を持つ方がいるみたいです。
しかも複数のサイトが記事を作成していたので、もしかしたら割と多くの就活生が自己分析に対してそのような感情を抱いているのかもしれませんね。
皆さんはどうですか?
気持ち悪いとまでは言わずとも、楽しくないとかやりたくないというようなマイナスの感情を抱いている方は多いのではないでしょうか。
私としては自己分析に対してマイナスの感情を抱く事は間違いではないと思います。
楽しくないものは、素直に楽しくないと思って問題ありません。
無理に自己分析は楽しいものだと気持ちを切り替える必要はないと思います。
なのでもし内定獲得の為に自己分析に対する気持ちを無理やりプラスの感情に変えようとしている方がいれば、それは止めた方が良いでしょう。
そして今回、一定数の就活生が自己分析に対して気持ち悪い等のマイナスの感情を抱いているかもしれないという予想から、自己分析に対して抱く感情について私の意見も以下の記事でまとめてみました。
もし興味があればご覧ください。
まとめ
今回は自己分析について私が当時実際にやって良かったと思える進め方を5つ紹介しました。
ポイントをまとめますと以下の通りです。
- 楽しかった事、成果を出せた事から考え始める
- 思い出せるだけ記憶を遡る
- 分析方法の型を作る
- 「なぜ?」と自分に問い続けて深く分析する
- 他人から見た自分についても把握する
自己分析は就活の中でもかなり面倒臭い部類の作業ではありますが、内定獲得を目指す上で重要な作業です。
面倒臭い気持ちをなんとか乗り越えて、少しずつでも良いので作業を進めていきましょう!